エチオピア

現在のエチオピア Yahoo Map
アフリカ大陸の東北、ナイル川上流の高原一帯を支配する。古代以来の歴史を有し、短い一時期を除いて、アフリカで植民地化しなかった国。1974年の革命で帝政から社会主義国に代わったが、1991年に政権が倒された。
- (1)古代 アクスム王国時代
- (2)近代 植民地化の危機
- (3)現代 帝政から社会主義国へ
エチオピア(1) アクスム王国時代
古代のエチオピア高原には、紀元前後から7世紀ごろまでアクスム王国が栄え、エジプトのコプト教会から東方系キリスト教を受容し、一時はアラビア半島まで支配した。
文明の段階になると、早くからエジプト文明の影響も受けていたと考えられるが、紀元前後のアクスム王国以来、独自の文化を継承し、独立を維持(もちろん紆余曲折はあるが)し、現代まで続いている。伝説では「シバの女王の国」といわれ、アラビア半島との関係が強い。
古代アクスム王国の時代
前1世紀頃までに成立したと思われる、最初のアクスム王国を建国した人々も紅海をはさんだアラビア半島南部から渡ってきたセム系民族とされる。紅海を利用したアラビアとの交易で繁栄し、プトレマイオス朝エジプトやローマ帝国とも交易を行った。3世紀にはローマ帝国の衰退に乗じて、紅海からインド洋に進出し、ビザンツ帝国やササン朝ペルシアとも盛んに交易を行った。彼らはアレキサンドリアで盛んだったキリスト教の単性説を受け入れ、エジプトのコプト教会のキリスト教信仰の影響を強く受けた、独自の東方系キリスト教会をつくり、信仰をつづけた。
7世紀以降はイスラーム帝国が成立し、アクスム王国は衰退した。西隣のスーダン方面からのイスラーム教の浸透が続いたが、エチオピアは高原地帯であるという地形的な条件もあってその浸透の度合いは低く、その後も変遷を遂げながら王国とキリスト教信仰を存続させてきた。エチオピアは民族的にはセム語系アムハラ人が多数を占め、現在はエジプトのコプト教会とも分離した東方教会系のキリスト教であるエチオピア正教会の信徒が多い。
Episode 「シバの女王の国」エチオピア
(引用)エチオピアは『シバの女王の国』と呼ばれてきた。伝説によると、紀元前10世紀、英明で名高いエルサレムのソロモン王のもとを訪れた南アラビアのシバ王国の美しい女王とのあいだにできた男子メネリクが、後にエチオピア王国を開いたとされる。これはあくまで伝説での話だが、こうした伝説が成立する背景として、古代エチオピアにおけるヘブライ文化(エチオピアにはファラシャと呼ばれるユダヤ教徒が存在してきた)の影響や紅海をはさんだ南アラビア文化との活発な地域交流が指摘できる。<宮本正興/松田素二『新書アフリカ史』1997 講談社現代新書 p.158 2018改訂新版ではp.182>→ イエメンの項を参照
ソロモン王朝の伝承
1137年頃、アクスム王国はクシ系のザグウェ朝によって滅ぼされた。この時代も東方教会系のキリスト教信仰が続き、岩盤をくりぬいた教会が各地に造られた。次いで1270年にシュワ地方のアムハラ人を基盤にしたイェクノ=アムラクが皇帝として即位し、「ソロモン王朝の復活」とした。ソロモン王朝とはエチオピアの最初の王メネリクがソロモンとシヴァの女王の間に生まれたという伝承に基づいている。エチオピア人とユダヤ人が紀元前から関係があったことは事実であろうが、エチオピアという国家自体の起源をソロモン王に求める「セム的歴史観」は、イデオロギーとして構築されてきた「神話」である。近代のエチオピア帝国でも、1889年に皇帝となったメネリク2世が「ソロモン王朝」の後継者と称したが、同様に「万世一系」の伝承を国家統合の公的イデオロギーとして利用したのだった。ヨーロッパ人の来訪
ヨーロッパ人の中に、アフリカ内陸の状況に対する関心が起こってきたのは、まず15世紀、ポルトガルがアフリカ西海岸に侵出し、奴隷貿易などを開始してからだった。初めはアフリカのスーダン(現在のスーダンではなく、サハラ以南の広範なアフリカを指していた)に産出する金への関心とともに、アフリカ内陸にキリスト教国があるというプレスター=ジョンの伝説があったからだった。当初は中央アジアに想定されていたが、モンゴルとの交渉が始まって実在しないことが判り、15世紀からはアフリカ内陸にあるのではないかという、期待が生じていた。ポルトガルのジョアン2世は、アフリカ西岸を南下させる海洋探検とは別に、陸路でエチオピアへの探検使節を派遣した。1487年5月、ペロ=デ=コヴィリャンとアフォンソ=デ=パイヴァはリスボンを出発し、地中海を通りアレクサンドリア、カイロを通って、アデンに着き、分かれてパイヴァはエチオピアに向かった。コヴィリャンはアデンから海路インド東岸に着き、カリカット、ゴアを訪れた後、カイロに帰着した。コヴィリャンはそこでパイヴァがエチオピアで亡くなったことを知り、ホルムズを経由してメッカやシナイ山をめぐった後、エチオピアに入り皇帝に謁見した。しかし帰国することを認められず足止めされ、1526年にエチオピアを訪れたポルトガル使節と対面して生存が確認されたが、すっかりエチオピア人になりきっていたと言い、そのまま現地で死去した。このコヴィリャンのインドに到達したことはポルトガル使節によってポルトガルにもたらされ、ヴァスコ=ダ=ガマのインド航路開拓とともに貴重な情報源となった。
エチオピア(2) 植民地化の危機
19世紀末から帝国主義の脅威が及び、アフリカ分割が進行する中、1896年、アドワの戦いでイタリアの侵略軍を破り、植民地化を免れた。しかし、1935年にムッソリーニのイタリアによって併合された。
そのころエチオピアにとってもう一つの脅威であったのが西に隣接するスーダンで大きな勢力となったマフディーの反乱であった。彼らは一種の宗教国家を作り、反英を掲げて戦っていたが、さらにジハード(聖戦)を掲げて東方系キリスト教国であるエチオピアに進撃してきた。マフディー軍との戦いは一進一退を続けたが、1889年にエチオピアのヨハネス4世が戦死するという打撃を受けた。代わってエチオピア南部のショア地方の藩主が立って皇帝メネリク2世となり、植民地化の危機に立ちむかうこととなった。
イタリアの侵出
1889年に皇帝となったメネリク2世は、国内に統一的権力を確保するため、イタリアの助力をあおぎ、同1889年5月2日にウッチャリ条約を締結した。その条約でメネリクは皇帝の地位を認められたが、イタリア側は事実上の保護国化を約束させたととらえた。また、イタリアがすでに支配していたエチオピアの紅海海岸一帯のエリトリア領有を確保した。エチオピアの東部の「アフリカの角」一帯は、ジブチがフランス領、ソマリランドは北部がイギリス、東部がイタリアによってそれぞれ植民地として分割されることとなった。 → アフリカ分割皇帝メネリク2世は、外圧を利用しながらエチオピアの統一と国力増強のための近代化に努め、首都アジスアベバ(アムハラ語で「新しい花」の意味)を建設、郵便、銀行、鉄道、道路などの事業を推進、特に軍隊の近代化と増強に努めた。その成果はイタリアとの戦争の勝利となって現れた。
アドワの勝利 イタリアはウッチャリ条約に基づき、保護国化を進めようとしたが、その条文の現地語アムハラ語訳文には保護国とするととれる語がなかったことから、メネリク2世はイタリアの要求を断固として拒絶した。イタリアは条約違反を口実に軍事行動を開始、それが1896年3月のアドワの戦い(第1次イタリア=エチオピア戦争)であった。この戦いはエチオピア軍の勝利となり、イタリア軍は1万7千の全部隊の4割を失って壊滅した。これはヨーロッパに対する「ハンニバル以来アフリカが勝ち取った最大の軍事的勝利」と言われる。この勝利によって、エチオピアは完全な独立国であることが承認された。<宮本正興/松田素二『新書アフリカ史』1997 講談社現代新書 p.306 2018改訂新版ではp.330>
エチオピア帝国は国際的にもアフリカの独立国として承認され、1923年には国際連盟に加盟した。メネリク2世の死後は、その娘が女王となり、摂政役を務めた若いラス=タファリが1930年に皇帝ハイレ=セラシエ1世として即位した。
ムッソリーニによる征服 しかし、そのころ、イタリアではファシスト党が急速に台頭してきた。ファシストは、政権を握ると軍事国家化を進め、アドワの復讐を唱えて国民の支持を得ようとした。権力をにぎったムッソリーニは、1935年10月、再びエチオピアに侵攻(第2次イタリア=エチオピア戦争)を開始し、1936年にはエチオピアを併合してしまった。1936~42年の間はエチオピアはイタリアとの連合王国という形態をとったが、事実上は植民地として支配されることとなった。
エチオピア(3) 帝政から社会主義国へ
第二次世界大戦後、ハイレ=セラシエ皇帝の下で帝政が行われたが、1974年に社会主義政権が成立して、帝政は崩壊した。このエチオピア革命で社会主義軍事体制が生まれたが、北のエリトリア、東のソマリアとの紛争が相次いでいる。
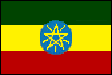
ハイレ=セラシエ1世
1941年に皇帝に復位したハイレ=セラシエ1世は、第二次世界大戦後のアフリカ諸国の独立の気運の中で重要な役割を果たし、1963年にアフリカ独立諸国首脳会議を主催、アフリカ統一機構(OAU)の設立にも尽力した。彼は対外的には開明的な君主として見られていたが、エチオピア国内では専制君主としてふるまい、その基盤にはグルトと呼ばれる藩主が領主に土地を与え、領主は農民から50~70%の小作料を取るという封建制度そのもの社会があった。さらに1970年代初頭には東アフリカの旱魃がエチオピアにも及び、農村の飢餓、都市の食料品不足と物価高が民衆の不満をさらに強めることとなった。また、1952年からエチオピアとエリトリアによる連邦国家という形態をとっていたが、エチオピアはセム語系アムハラ人などからなる民族構成であるが東方教会系のキリスト教が多いのに対し、北部のエリトリアは紅海を隔ててアラビア半島と関係が深く、アラブ系住民のイスラーム教徒も多いため、国家的な一体感を維持するのは困難だった。1962年、エリトリアの議会が分離独立を議決すると、エチオピアは軍隊を派遣して併合し、エリトリア州として支配することを強行した。それに対するエリトリアの分離独立運動が激しくなった。
Episode エチオピアの英雄「裸足のアベベ」
エチオピアというと、日本人にはいまだに「裸足のアベベ」こと、アベベ=ビキラを思い出す人が多いに違いない。アベベは1960年のローマ・オリンピックと1964年の東京・オリンピックのマラソンで二連覇したマラソンランナー。何といっても印象深いのはローマで、無名だったアベベが、裸足で走り優勝したときだった。世界中の人が驚いたが、特にエチオピアでは一躍国民の英雄になった。それは、かつてエチオピアに攻め込み、一時支配したイタリアの首都ローマで、エチオピア人が優勝したからであった。世界のマスコミはそんなことより、裸足だったことや高地人が優勝したことを騒ぎ立てた。裸足で走ったのは偶然靴が壊れ、新しいものを買うヒマがなかったかららしい。早速世界の運動靴メーカーがシューズの提供を申し出たそうだ。マラソンで高地トレーニングが取り入れられることになったきっかけもアベベの優勝だった。アベベは東京でも優勝して二連覇し、日本にも馴染みが深くなった。しかしハイレ=セラシエ皇帝の親衛隊の兵士だったアベベは、まもなく祖国エチオピアが内戦状態になると、不遇のうち1973年に41歳の若さで亡くなった。その翌年には皇帝もその位を追われることとなった。エリトリア独立運動
1962年にエチオピアがエリトリアを一方的に併合したのは、紅海への出口を確保するためであり、またエチオピアに軍事援助を行っているアメリカが、エリトリアを対アラブ、対アフリカの戦略拠点として自由に使用できることをねらったものであった。エチオピアの一州となったエリトリアでは、その主権を奪われ、自治も認められない状態となったため、エリトリア独立運動が激しく展開されるようになった。60年代にはエリトリア解放戦線(ELF)が武装ゲリラ活動を開始、70年代にはエリトリア人民解放戦線(EPLF)が独立と社会改革を掲げて独立運動の中心勢力となっていった。エチオピア革命
エリトリアの独立闘争が激しくなる一方、エチオピア国内では皇帝政治の封建的社会経済体制のもとで、失業や飢饉が続いていることに対する不満が強まっていった。1974年2月、首都アジスアベバで労働者、市民、学生の大規模なデモが自然発生的に始まり、各地の兵士がそれに合流した。軍の若手将校団(軍事委員会=デルグといわれた)が帝政打倒に踏みきり、1974年9月12日にクーデタによって皇帝ハイレ=セラシエ1世(82歳)を廃位、軍政が敷かれることとなった。帝政との妥協を図る穏健派に対して、メンギスツ大佐の主導する軍事委員会(デルグ)がクーデタを決行し多数の穏健派を殺害し、翌年には前皇帝も殺害した。1977年にはメンギスツは軍事独裁政権を樹立し、ソ連・キューバなどの社会主義国家の支援を受け、マルクス・レーニン主義を掲げる人民民主主義国家とすることに成功した。
メンギスツ軍事政権は主要産業の国有化や農地改革などの社会主義政策を強権的に推し進めたが、同時にエリトリア独立戦争が続いているだけでなく、1977年からは東部のソマリアとの国境紛争であるエチオピア=ソマリア戦争(オガデン戦争)も始めたため、経済の悪化、社会不安が次第に強まることとなった。1980年代半ばにも旱魃が起こり、このときはエチオピアだけで実に約100万の犠牲者が出た。<宮本/松田『前掲書』旧版p.521 改訂新版p.576>
にもかかわらずメンギスツは1987年には大統領に選出され、エチオピア人民民主共和国と国号を変え、労働者党による一党独裁体制を固めた。
エチオピア=ソマリア戦争
1977年~88年、東部アフリカの「アフリカの角」といわれた地域の二国、エチオピアとソマリアの間で国境紛争から拡大した戦争。エチオピア東部オガデン地方ののソマリ人がソマリアへの統合を求め、ソマリアがそれを支援したことから始まった戦争であるので「オガデン戦争」ともいう。背景には東方系キリスト教徒の多いエチオピアとイスラーム教徒の多いソマリアの宗教的対立、冷戦末期の東西対立、アラブ諸国の利害などがあったが、両国とも当初は社会主義を掲げる軍事独裁政権下にあり、ソ連とも良好な関係にあったことから、複雑でわかりにくい展開となった。戦争の経緯 エチオピアの東部、ソマリアと接するオガデン地方には多数のソマリ人が居住していた。彼らはエチオピアからの分離とソマリアへの併合を求めるようになった。ソマリアの軍事独裁政権バーレ大統領は「アフリカの角」に広がっているソマリ人(古代にアラビア半島から移住したとされる)の統合を主張して、国境の変更を要求、両国の国境紛争はついに1977年からエチオピア=ソマリア戦争(オガデン戦争)となった。エチオピアでは1974年に皇帝を退位させたメンギスツの率いる軍事政権も社会主義国家建設を目指していたので、ソ連・キューバの支援を受けて軍備を増強し、激戦となった。
東西冷戦の代理戦争へ ソマリアも当初はソ連の支援を受けていたが、アメリカ合衆国など西側諸国とサウジアラビアなどのアラブ諸国は、ソマリアへのソ連の影響力が強まることを恐れ、ソ連に代わって武器と資金の援助を働きかけた。アラブの産油国の一角に食い込むような「アフリカの角」が共産化することを最もおそれたのだった。このため、この戦争はアフリカにおける東西冷戦下の米ソ代理戦争という様相を呈することになった。また中ソ対立の最中であったため、中国もソマリアを支援した。しかし、戦争はソ連軍に支援されたエチオピア軍が物量ともに優勢で、オガデン地方のソマリア軍が撃退されたため、1988年4月4日にに講和が成立、エチオピアの軍事政権は体制を維持することができた。ソマリアは長期にわたる戦争によって疲弊し、バーレ大統領の独裁政治に対する不満も高まって反政府活動が活発化し、同1988年6月からソマリア内戦に突入、泥沼の状態となっていく。
軍事政権の崩壊
しかし一方のエチオピアにおいても、1991年、ソ連邦の崩壊によって後ろ盾を失ったメンギスツ政権は一気に倒れることとなった。同年、エリトリア人民解放戦線とエチオピアの反政府勢力は協力して首都アジスアベバを攻撃、占領した。そのためメンギスツはジンバブエに亡命し、社会主義軍事政権は崩壊した。それを受けて1993年には国連の監視下のもとで、国民投票が実施され、エリトリアの分離独立が承認された。新たな連邦国家へ 反政府勢力を結集したエチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)の暫定政権が成立、メレス=ゼナウィが暫定大統領となり、1995年に新憲法が制定されて、エチオピア連邦民主共和国となった。メレス=ゼナウィ政権は、各民族集団に連邦を離脱する権利を認め、従来のヨーロッパ人が定めた国境による国家建設の道ではない、新しい国家建設をめざした。
エリトリアとの国境紛争再燃 民族自決を保障する連邦共和国という、ユニークな国づくりが注目されたが、エチオピアとエリトリアの「蜜月時代」は長く続かず、新たな対立が起こってしまう。エリトリア独立によって紅海への出口を失ったエチオピア側の不満が表面化、バドメ地区の帰属をめぐる国境紛争が1998年に両国間の戦争に発展、両国空軍が互いに相手の首都を空爆するなど戦闘はエスカレートし、10万人を超える犠牲者が出てしまった。アフリカ連合(AU)の調停で、2000年に停戦合意が成立したものの、その後も小競り合いが続き、ようやく2018年、エチオピアのアビー首相がエリトリアを訪問、国交正常化を表明した。<宮本正興/松田素二『新書アフリカ史改訂新版』2018 講談社現代新書 p.332-333>
ソマリア内戦への干渉 隣国のソマリア内戦はさらに混迷の度を加え、2006年にはイスラーム原理主義に近いイスラーム法廷会議が首都モガディシオを占領、イスラーム法に基づく国家統一を掲げるに至った。それに対してキリスト教国であるエチオピアは強い危機感を抱き、アメリカの同調を得て、同年12月、空陸からソマリアに侵攻し、ソマリアの暫定政府軍とともに首都を制圧した。この軍事行動に対し、他のアフリカ連合諸国は強く非難したが、アメリカが支持したため国連で問題にされることもなく、ソマリアのイスラーム法廷会議は実力で排除されることとなった。しかし、ソマリアにおける反エチオピア感情は根強く、暫定政府もエチオピア軍の長期駐留は望まなかったので、2009年には撤退した。
しかしその後、ソマリアには新たなイスラーム過激派と言われるアルシャバーブなども台頭、内戦の収束への見通しには厳しい状況が続いている。
News エチオピア首相、ノーベル平和賞受賞
2019年10月11日、第100回目となるノーベル平和賞はエチオピアの現役首相アビー=アハメド=アリーに与えられることが発表された。アビー氏は43歳、エチオピアとエリトリアの国境を巡る対立に終止符を打ち、近隣諸国の紛争解決に仲介の努力を続けていることが評価された。エチオピア国内ではなおも言語の違いなどから部族対立が続いており、課題は残されているが、ノーベル委員会はアビー氏の平和構築に向けてのこれからの努力を後押しするための授賞であると述べた。エチオピアはこれまで少数民族のティグレが支配してきたが、アビー氏は最大民族オロモのイスラーム教徒、母はオロモに次ぐ多数派のアムハラのキリスト教徒で、複数の言語を話すことができ、融和を進める指導者としては適任と見られてきた。エリトリアとの国境紛争に兵士として従軍した後、政治家に転じ、2018年4月に首相となると、7月に電撃的にエリトリアの首都アスマラを訪問、イサイアス大統領と外交関係の正常化で合意、和平を実現した(上述)。さらに近隣のケニアとソマリアの国境紛争や、スーダン、南スーダンの紛争などの解決に向けて仲介し、国内政治では政治犯の釈放や女性の地位向上などの民主化に取り組んでいる。
1998年に始まったエリトリアとのバドメ地区を巡る国境紛争は2000年の停戦までに推定10万人が犠牲となった。ハーグの国境画定委員会は2002年にエリトリアのバドメ領有を認めたが、エチオピアが受け入れず膠着していた。アビー首相はバドメの放棄を決断、20年に及んだ対立を終わらせたのだった。ただし、まだ国境をこえる移動は空路を除いて認めておらず、エチオピア国内にも多数派オロモの中にアビー氏を裏切りとして非難する勢力もあるなど、完全解決には至っていない。<朝日新聞 2019年10月12日朝刊による>
最近のノーベル平和賞が、功績が確定した人物に与えられるのではなく、未完の平和構築に取組中の指導者に対し、激励の意味で与えられるという傾向がはっきりと現れている。
News エチオピア、再び軍事衝突
エチオピア北部のティグレ州でティグレ人民解放戦線(TPLF)の分離運動に対して、政府軍が2020年11月28日に攻撃を開始した。TPLFは少数民族ティグレ人のつくる政党で、長年エチオピアの与党連合の中心として権力をにぎっていたが、2018年に最大民族であるオロモ人のアビー氏が首相となってからは与党連合から離脱していた。アビー首相は2000年に隣国エリトリアとの国境紛争を解決し、平和をもたらしたことで2019年のノーベル平和賞を受賞しているが、ティグレ人との内戦では強硬姿勢をとり、武力行使を続けている。内戦の危機が強まる中、ノルウェーのノーベル賞委員会はアビー首相に暴力の停止を訴えているが、その姿勢は変わっていない。エチオピアの新たな内戦は犠牲者の拡大が危惧されている。<朝日新聞 2020/11/29>