モロッコ
イベリア半島とジブラルタル海峡で隔てられたアフリカ北西部の国。ベルベル人のムラービト朝・ムワッヒド朝以下、独自のイスラーム圏を形成した。近代ではスペイン、フランスが侵出し、その分割植民地支配を受け、第二次大戦後に独立した。
モロッコ GoogleMap
- (1)カルタゴとローマの支配
- (2)イスラーム化と王朝の交代
- (3)ヨーロッパ列強の侵出
- (4)フランスの進出と保護国化
- (5)フランスとスペインによる分割支配
- (6)モロッコの独立
世界史上のモロッコ
日本から遠く離れたアフリカの西北端と言うこともあってなじみが薄く、映画『モロッコ』や『カサブランカ』などで、異国情緒とロマンチックな雰囲気だけが思い出される向きもあるが、世界史上は大変重要なところであり、特に「ヨーロッパから見て最も近いアフリカ」という位置にあることを想起する必要がある。しかし、高校教科書では、前近代でムラービト朝・ムワッヒド朝がこの地とイベリア半島の双方を支配したこと、またモロッコがサハラ南部のアフリカ内部と盛んに交易し、時には軍事侵略を行ってガーナ王国やソンガイ王国を滅ぼしたことが出てくる程度であり、次にその名前が出てくるのは帝国主義時代にはフランスによって保護国化されたことと「モロッコ事件」の記述となる。それ以外では断片的に出てくるのみで、ほとんど取り上げられることがない。
受験という観点からは、上述の事項だけが必須事項であり、他は切り捨てて良い、ということになろう、しかし、ムラービト朝・ムワッヒド朝とはどんな王朝だったのか、その前後のモロッコはいったいどうだったのか、他にどんな王朝があったのか、またなぜ現在も王政が続いているのか、モロッコでは反植民地闘争はあったのか、などの興味がわいてくるのも当然である。普段の学習ではとてもそこまで手を回す余裕はないと思われるので、以下にモロッコの歴史で受験生としても知っておいて良い、興味深い事項にしぼってまとめてみた。
モロッコ(1)カルタゴとローマの支配
カルタゴとマウレタニア
この地にはベルベル人の居住地であったが、前9世紀ごろ海岸地方には東地中海岸のフェニキア人の植民活動が及んできて、植民市の中の最大のカルタゴの支配を受けるようになった。内陸部にはベルベル人のマウレタニア王国が生まれた。ローマの属州に
ポエニ戦争の結果、カルタゴが滅亡するとローマの属州アフリカ州の一部とされたが、1世紀の中ごろにはマウレタニア王国も滅ぼされて属州マウレタニアとされた。ローマ帝国が東西に分裂して西ローマ帝国の領土となったが、その支配力はすでに衰えており、429年にはゲルマン人のヴァンダル人がこの地を通って東に移動し、旧カルタゴの地にヴァンダル王国を築いた。ヴァンダル王国は、533年に東ローマ帝国(ビザンツ帝国)のユスティニアヌス帝に滅ぼされ、モロッコもその支配に入った。モロッコ(2) イスラーム化と王朝の交代
8世紀にイスラーム化する。その後、イドリース朝が自立、ムラービト朝とムワッヒド朝が繁栄する。
イスラームの進出
7世紀に成立したイスラーム教は、その信仰と政治を一体化させた帝国の支配を周辺に急速に拡大し、北アフリカでもビザンツ帝国を次第に駆逐していった。ウマイヤ朝は670年にチュニジアにカイラワーンを建設、マグリブ進出の拠点とし、8世紀初めに将軍ムーサーがモロッコを征服、さらに711年にはこの地からジブラルタルを超えてイベリア半島に広がっていった。こうしてアラブ人がベルベル人を支配する社会となってベルベル人のイスラーム化、アラブ人との同化が始まった。モロッコのイスラーム国家
しかし広大な領土もつに至ったアッバース朝は、都バグダードから離れた地域への統制を次第に放棄するようになり、各地に地方政権が登場するようになった。以下、モロッコの地に生まれたイスラーム教を奉じる諸国家の興亡は次のようにまとめることが出来るが、次第にアラブ人支配からベルベル人が自立していくこと、その際中央のスンナ派との関係で、イスラーム教の分派のシーア派国家が生まれたことなどに注意すること。- イドリース朝 8世紀の末には、第4代カリフのアリーの子孫がこの地で自立してイドリース朝として自立した。これは最初のシーア派国家であった。この王朝の都として建設されたのがフェスである。9世紀には内部対立から衰退し、チュニジアに起こったファーティマ朝によって926年に滅ぼされた。ファーティマ朝がエジプトに移動した後のモロッコにはベルベル人の小国家分立が続いた。
- ムラービト朝 西サハラの遊牧ベルベル人の中に起こった厳格なスンナ派信仰を掲げた教団が、1056年に建国した。ムラービトとは、修道士を意味するムラービトゥーンから来ている。かれらは周辺の異教徒に対する聖戦を展開、まずサハラ南部のガーナ王国を征服、さらに北上してモロッコを征服して、新都マラケシュを建設した。さらに1086年にはイベリア半島に入り、キリスト教勢力を破り、そのレコンキスタ運動を一時後退させた。ムラービト朝はこうしてジブラルタルをはさんで両大陸を支配する国家となったが、イベリア半島のアンダルスの都市生活に順応していく内に、信仰上の純粋性と遊牧民としての戦闘性が次第に薄くなり、弱体化した。
- ムワッヒド朝 ムラービト朝は遊牧ベルベル人主体の国であったのに対し、定着民のベルベル人部族の一つが1146年にマラケシュを占領して建てたのがムワッヒド朝。ムワッヒドとは、神の唯一性を信ずる人の意味のムワッヒドゥーンから来ていおり、やはり宗教的な結束の強い国家であったが、ムラービト朝がスンナ派でありアッバース朝カリフを認めたのに対して、ムワッヒド朝はスーフィズムの影響を受け、またシーア派にも近かったのでアッバース朝を認めず、自らカリフと称した。またその領土はマグリブ地方のアルジェリア、チュニジアに及び、またムラービト朝と同じくジブラルタルを超えてイベリア半島南部(アンダルス)をも支配したが、サハラ以南には領地は及ばなかった。ムワッヒド朝の下でイブン=ルシュド(アヴェロエス)がどが活躍し、西方イスラーム文化が開花した。12世紀のムワッヒド朝全盛期の王がヤークーブ=アルマンスール王で、彼はイベリアでキリスト教軍に大勝し、セビーリャやラバト(現在のモロッコの首都)に大モスクを建設した。しかし、再びキリスト教勢力の国土回復運動が活発となり、1212年にラス=ナバス=デ=トロサの戦いでキリスト教国連合軍に敗れてイベリア半島から撤退し、1269年にマリーン朝に滅ぼされた。
- マリーン朝 モロッコに登場したムワッヒド朝の後継国家の一つ。メリニッド朝ともいう。1248年にフェスを都として自立し、69年にマラケシュを征服してムワッヒド朝を滅ぼした。都はフェスに置かれた。この王朝の14世紀にタンジールで生まれたのがアラブの大旅行家として知られるイブン=バットゥータである。彼は三大陸にわたる大旅行を行ってフェスに戻り、マリーン朝の君主の求めに応じて旅行記を口述した。マリーン朝は1471年まで存続したが、その一族が建てたワッタース朝(1471~1550)に交替した。しかしこの王朝の時代は部族対立のため不安定であった。
モロッコ(3) ヨーロッパ列強の侵出
15世紀からポルトガル、スペインの侵出始まる。サード朝のもとで抵抗を続けるが、18世紀以降イギリス、フランスなどの列強が勢力を及ぼす。
ポルトガル・スペインの侵出
アフリカの地中海岸は、16世紀中ごろまでにアルジェリアまでがオスマン帝国に征服されたが、モロッコにはその支配は及ばなかった。しかし15世紀から大航海時代を迎えたポルトガルのエンリケ航海王子による西アフリカ進出が開始され、まず1415年、ジブラルタル海峡に面したセウタを占領した。ポルトガルのモロッコ侵出の狙いは、当初はアフリカ内陸からもたらされる金やモロッコ沿岸の穀物資源であった。1471年にはタンジール(現在のタンジェ)を征服した。エンリケ王子の下で、ポルトガルの狙いはモロッコ内陸部から、次第にその大西洋岸を南下して新たな資源を得ようとすることに移って行き、基地を設けながらアフリカ西岸の南下をすすめていった。その頃隣国のスペイン(カスティーリャ)はレコンキスタの最終段階に入り、1492年にグラナダのナスル朝を滅ぼして、それを完了させた。スペインはイベリア半島のイスラーム勢力を駆逐すると、モロッコやアルジェリアに勢力を伸長しようとしてきた。セウタは1580年にポルトガルがスペインに併合された結果、スペインの領土となり、ポルトガル独立(1640年)後もスペイン領にとどまることとなった。
サード朝の西アフリカ支配
東方から迫るオスマン帝国と、北方から迫るポルトガル・スペインというモロッコの危機に登場したのがサード朝(サーディ朝ともいう)であった。モロッコ南部サハラに面したドラ地方のシャリーフ(ムハンマドの血を引くとされた名家)であったサード家はポルトガルに対するジハードを開始し、アガディールなどを奪還(1541年)し、1549年に建国した。サード朝はマンスール(勝利者の意味。在位1578~1603)の時、西サハラにマスケット銃(火打ち石銃)で武装した白人傭兵(イベリアから逃れてきたアンダルシア人ムスリム)を遠征軍として送って1591年にソンガイ王国を滅ぼし、金や奴隷を手に入れ、盛んにサハラ交易を行って繁栄した。サード朝はトンブクトゥとジェンネに太守(パシャ)を置いて統治したが、マンスール王の死後は内紛で支配力が弱まり、1612年以後は現地人がパシャに任命されるようになった。その後もモロッコの名目的な統治は1833年まで続いた。鎖国と開国
1659年、サード朝が倒れ、アラウィー朝(アラウィット朝ともいう)が成立したが、18世紀にはヨーロッパ各国の経済進出が著しくなり、1757年のデンマークを初めとする諸外国との通商を開始し、1777年にはアメリカ合衆国の最初の承認国となった。しかし、18世紀末に地方の部族間の争いが激しくなるとアラウィー朝は鎖国政策を採ってタンジール港だけを開港地として他の港での通商を断った。19世紀中ごろになると外圧が強くなり、不平等な通商条約をイギリスとは1856年、フランスとは1863年に締結させられた。スペインはセウタで境界紛争を引き起こして1859~60年にモロッコに出兵、モロッコ戦争(アフリカ戦争とも言う)を引き起こし、61年に通商条約を締結した。こうしてモロッコは開国し、イギリス・フランス・スペインとの不平等条約に苦しめられ、アラウィー朝は近代的改革を試みたものの不十分で、外債が累積し財政危機に陥った。このようななか、モロッコでも外国人排斥や列強に妥協的な王朝を否定する民衆の抵抗運動がスーフィズム教団に指導された宗教運動として起こってきた。
モロッコと日本
日本が安政の五ヵ国条約でアメリカ、イギリス、フランスなどと通商条約を結んだのが1858年であり、日本の開国はモロッコの開国と同じ時期であった。この両者では、鎖国政策から不平等条約による開国、そして外国人排斥運動(攘夷運動)が権力を倒す目的で展開されている。このように危機的状況には似ているところもあったが、しかし、モロッコと日本は結局違った道を歩むこととなった。その違いは何であったか。ともすれば日本人の強さや明治の指導者の力量への称賛になりがちであるが、単純に列強からの距離による違いだけなのではないだろうか。モロッコはフランス、スペイン、イギリスになんとしても近すぎた。日本は遠かった。この様な地理的条件を考慮せずに、両者を単純に比較することは出来ないだろう。モロッコ(4) フランスの侵出と保護国化
19世紀後半から、帝国主義列強の侵出が激化。特にフランスとドイツがモロッコ事件で衝突した後、フランスの保護国となる。
帝国主義諸国の侵出
特にフランスは1830年以来、隣接するアルジェリアを植民地支配していたので、モロッコにも重大な関心を寄せていた。普仏戦争に敗れて国際的地位が低下すると、戦後成立した第三共和政政府はインドシナへの侵出に加え、アフリカでもチュニジアやマダガスカル領有と共にモロッコへの侵出による植民地帝国の形成を図り、さらにサハラから東岸のジブチに向かうアフリカ横断政策を採った。そのアフリカ政策は1898年のファショダ事件でイギリス帝国主義との対決の危機を迎えたが、両国は見事な帝国主義的妥協を図った。その後フランスは、イタリアとの秘密協定でフランスはモロッコに、イタリアはトリポリにそれぞれ権益を持つことを相互に認めた上で1904年の英仏協商でイギリスのエジプト権益を認める代わりにモロッコでの権益を認めさせるという勢力圏協定を結んだ。同年、スペインとの間でモロッコでの勢力圏の分割を取り決めた。こうしてモロッコは帝国主義諸国によって「分割」支配される国際的環境に置かれることとなり、フランス・ドイツ間に二次にわたるモロッコ事件が勃発した。
Episode 熊蜂の巣モロッコ、きだ・みのるの目
(引用)現世紀(20世紀)初頭の前後に王位にあったアジス王(1894-1909)の時代になると、王権は弛み、王位の覬覦(きゆ、下のものが上のものをのぞむこと)者が輩出し、内乱が起こり始めた。これを見て欧州列強は植民地としてこの国に目をつけ始めたが住民の精悍さと列強の利害の錯綜のため――すべての弱体政府がそうであるように、モロッコ政府も保身上、以夷制夷政策(夷を以て夷を制する策)を採っていた――モロッコは熊蜂の巣モロッコと呼ばれ、手をつけた国は必ず手を焼くと考えられていた。<山田吉彦『モロッコ』1951 岩波新書 p.43 著者の山田吉彦はきだ・みのるのもう一つの筆名>
第一次モロッコ事件
モロッコ分割に遅れて手を出し、新たな植民地帝国を目指したのがドイツのヴィルヘルム2世であった。フランスの同盟国ロシアが日露戦争で苦戦している形勢を見たヴィルヘルム2世は1905年3月31日、自らモロッコのタンジールに上陸してスルタンと会見、フランスのモロッコ支配を牽制、第1次モロッコ事件(タンジール事件)を引き起こした。これは「モロッコ問題」という国際紛争となり、翌1906年にアルヘシラス会議が開催され、モロッコも参加した上で、列強は機会均等・門戸開放と共にモロッコの主権尊重を取り決めたが、実質的にはフランスとスペインの警察権などの権益が認められ、ドイツは孤立した。Episode 珍しいベルベル人を主人公とした映画『風とライオン』
1975年に制作されたアメリカ映画『風とライオン』は1904年のタンジールを舞台としており、大げさに言えば帝国主義を批判する視点から作られている。なにより興味深いのはショーン=コネリーが迫力たっぷりに演じている主人公が、「ライオン」に喩えられるベルベル人の盗賊(というより民族指導者。ムハンマドの子孫を自称している。)であることだ。そして「風」に喩えられるのは、アメリカ大統領セオドア=ローズヴェルトだ。キャンディス=バーゲンの女ながらの立ち回りも面白いが、当時のモロッコ国王の頽廃ぶりや、同時期の日露戦争の援助を依頼にワシントンに来ていた金子堅太郎を思わせる日本人が出てきたり、世界史を勉強するにもうってつけの映画なので、ぜひ一見してほしい。
モロッコの民族運動
1909年 スペイン領のメリリャ鉱山で現地労働者が賃上げ闘争にはいると、スペイン政府は軍隊を派遣して鎮圧した。この時スペインでは労働者が派兵反対に立ち上がり、ゼネストで抵抗した。それに対して政府は戒厳令を施行してバルセロナでは砲兵を出動させて反乱を鎮圧、アナキストをその指導者として捕らえ処刑した。これはスペインの「悲劇の一週間」といわれ、労働運動・民主化運動が押さえられ右傾化するきっかけとなった。第2次モロッコ事件
アルヘシラス会議の結果に不満なドイツのヴィルヘルム2世は、モロッコにおける反仏民族運動を扇動する目的で、1911年7月1日に軍艦一隻をアガディールに派遣した。それが第2次モロッコ事件(アガディール事件)である。この挑発を受けたフランスでも国論が沸騰し、独仏戦争の開始直前までいったが、年末に妥協が成立しフランスはコンゴの一部をドイツに譲ることでモロッコ支配を認めさせるという、これまた帝国主義的な取引によって事態を収束させた。モロッコの保護国化
フランスのポワンカレ内閣は1912年にアラウィー朝スルタンとの間でフェス条約を締結し、モロッコ保護国化を実現させた。これによってモロッコは主権を喪失し、国土は大半を占める「フランス領モロッコ」と、北モロッコの一部(リーフ地方)と西サハラの「スペイン領モロッコ」に分割された。1912年のフランスのモロッコ保護国化に対して、直ちにモロッコの民衆的抵抗が始まった。フランスはそれを鎮圧するためにリオテを総督に任命し、リオテは典型的な保護国統治を行った。
(引用)かくしてフランスのこの新しい保護国には保護を快しとしない民がなくはなかった。民衆の不満はこの条約(フェス条約)に署名した王に向かって爆発した。4月17日首都フェスの軍隊は、軍の指導、教育に当たっていたフランス人将校十三、下士四〇、仏市民十三を殺害して、王に叛いた。同月二八日フランスのレンヌの第十部隊長をしていたリオテーは同月二八日モロッコ総督に任命され、在仏一カ年ばかりで再びアフリカに戻ることになった。彼の最初の役割は首都のフェスに侵入した聖戦の騎士二万を掃蕩し、聖戦運動の拡大を阻止することであった。・・・<山田吉彦『モロッコ』1951 岩波新書 p.43>
モロッコ(5) フランスとスペインによる分割支配
モロッコは北西部のスペイン領を除き、1912年からフランスが保護国として支配、それに反発する民族抵抗運動も続いた。
リーフ戦争
1920年にスペイン領モロッコで起こった植民地支配に対する抵抗がリーフ戦争であった。指導者であるアブデル=カリムはリーフ共和国の独立を宣言してスペインに反旗を翻し、その勢いはフランス領に及んできた。リーフ共和国はソ連の承認を受け、その支援で戦ったが、1925年にフランスとスペインの連合軍の総攻撃を受けて崩壊した。Episode モロッコ人の出てこない映画『モロッコ』
ゲーリー=クーパーとマレーネ=ディートリヒが共演して有名になった映画『モロッコ』(監督ジョセフ=フォン=スタンバーク)は、1930年に製作されたが、フランス植民地支配に抵抗するベルベル人を抑圧するために雇われた傭兵部隊、いわゆる外人部隊が舞台となっている。外人部隊に砂漠にまでついていく商売女たちのすさまじい根性が描かれている。しかしこの映画は題名通りモロッコが舞台となっているが、外人部隊の戦う相手であるモロッコ人(ベルベル人)はほとんど出てこない。
ベルベル勅令反対運動
フランスはリーフ戦争後の1930年、モロッコに対して「ベルベル勅令」をスルタンの名で発した。それはベルベル人の居住地にはなお、文化人類学者クリフォード=ギーアツは『二つのイスラーム社会』で、ベルベル勅令反対運動を指導したアル=ファッスィーらを聖典主義運動として分析している。聖典主義とはイスラーム復古主義のことであろう。
(引用)大衆のデモが主要な都市と町に爆発し、(毎週金曜の)公式礼拝の折には神罰がフランスの上に下し置かれるようにという祈祷が全国で捧げられ、アル=ファッスィとその同志は主要なモスクの前で大聴衆を集めて長広舌を振るった。事態は、汎イスラーム運動のとりあげるところとなって、モロッコの国境を越えて各地に飛火し、イスラームのためにベルベル人に手を伸べるための委員会が、エジプト、インド、そしてさらにインドネシアにさえ誕生した――これは私の知る限りでは、モロッコとインドネシアがただ一度だけもった直接の歴史的関係であった――。<クリフォード=ギーアツ『二つのイスラーム社会』1968 岩波新書 p.136-140>しかし、30年代、40年代に次第にスルタンの重要性が大きくなり、原初イスラームを復活するという動向は中心からそれていった。1953年フランスに退位させられたムハンマド5世の民族運動の中での指導力が強まり、追放されて2年ちょっとして独立モロッコの主催者となるべく帰還したときには、彼は絶大な大衆的英雄になってしまった。ギーアツに依ればそれこそ「マラブーの王」つまり聖者崇拝の復活だったという。
スペイン内戦とモロッコ
1936年、スペインの人民政府に対する右派の反乱は北モロッコのスペイン軍のビダル将軍によって起こされた。当時カナリア諸島にいたフランコ将軍が反乱に呼応し、スペイン内戦が勃発、モロッコは反乱軍の拠点となった。スペイン国内に進撃したフランコ軍には多数のモロッコ人兵士が加わった。1939年に人民戦線内閣が倒れ、反乱軍の勝利となり、フランコ将軍の独裁政治が行われることとなった。第二次世界大戦とモロッコ
フランス保護国モロッコではカサブランカが商業港として繁栄していたが、第二次世界大戦が勃発し、ナチス=ドイツがフランスに侵攻、1940年7月親独政権のヴィシー政府が成立すると、モロッコも北アフリカのドイツ勢力圏に入ることとなった。1941年11月にはアメリカ・イギリスなど連合軍は、北アフリカ作戦(トーチ作戦)を開始、モロッコ・アルジェリアに上陸し反攻を開始した。モロッコのカサブランカにはアメリカ軍が上陸、フランス・ヴィシー政府軍と交戦したが、フランス軍はまもなく停戦に応じ、モロッコは解放された。Episode 映画「カサブランカ」
カサブランカは、ヨーロッパから遠く離れた西アフリカの港町であるが、第二次世界大戦中には、親ドイツのフランス・ヴィシー政権下にあったものの、ヨーロッパの戦火を逃れた人びとや中立国ポルトガルを経由してアメリカに渡ろうとする人びとが押しよせ、国際的な謀略の渦巻く都会となっていた。その街と時代を舞台にした映画がイングリット・バーグマン、ハンフリー・ボガード主演で人気が高い「カサブランカ」である。もちろん二人の恋物語なのだが、1942年に制作されたという背景から、当時の緊迫した政治情勢がもう一つのドラマの柱になっている。あの名曲、 As Time Goes By と共にラブロマンスを楽しむと共に、世界史の勉強として観るのもよいのでは。カサブランカ会議 1943年1月14日~26日、モロッコのカサブランカでイギリス首相チャーチルとアメリカ大統領フランクリン=ローズヴェルトのカサブランカ会談が開催された。これは連合国の戦後処理構想を協議したもので、北アフリカ作戦に続き、シチリア島上陸を行うことなどを決定した。
モロッコ(6) モロッコの独立
1956年、フランス保護領からモロッコ王国として独立した。西サハラとの領土問題、イスラーム過激派の台頭など、不安定要素も続いている。
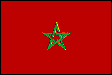
ムハンマド5世とスルタン位
ムハンマド5世(ムハンマド=ベン=ユースフ)はモロッコ王国の独立の英雄とされ現在も国民的な人気が高い。彼はスルタンの正当性をスンナ派の原理であるバイア(合意、協定ないし忠誠を誓うことの意味)に求めると同時に、この国の筆頭マラブー(聖者)の地位にある者という権威付けを行い、1957年にはスルターンの称号を廃して正式に国王となった。また王位継承に冠して1961年には長子相続制を定めて王位を安定させた。<このあたり、クリフォード=ギーアツ『二つのイスラーム社会』1968 岩波新書 p.132-133 などによる>彼は建国の英雄とされ、現在でも首都ラバトの国際空港は「ムハンマド5世空港」と言われ、国立大学も「ムハンマド5世大学」と言われている。モロッコのアラウィー朝の王位は、1961年にムハンマド5世の死去に伴い、ハッサン2世が即位、1999年よりムハンマド6世となっている。
西サハラ紛争
現在のモロッコが抱える最大の問題は西サハラ領有問題であろう。西サハラは旧スペイン領であるが、モロッコ独立の際に帰属が決められていなかった。1970年代かモロッコに西サハラ併合の運動が起こり、1975年にスペインが西サハラのモロッコとモーリタニアに割譲することを決めて撤退すると、モロッコは「緑の行進」と称して非武装越境大行進を行った。隣接するモーリタニアも領有を主張して北上した。西サハラ住民はアルジェリアに逃れ、翌76年、独立を目指す勢力はポリサリオ戦線を結成、亡命政権の樹立を宣言し、西原でのモロッコ・モーリタニアに対するゲリラ闘争を開始した。ポリサリオ戦線との戦いに手を焼いたモーリタニアは79年に撤退、その後はモロッコ軍が進駐して実効支配している。モロッコの西サハラ実効支配 モロッコは現在も形の上では西サハラの8割を実効支配しており、リン鉱石などの資源を管理している。しかし、ポリサリオ戦線を支持しているアルジェリアとの関係は一時悪化した。また、1984年にアフリカ統一機構(OAU)がポリサリオ戦線の西サハラ独立を認めたので、モロッコはその創設メンバーであったが脱退した。国連の仲介によって1990年代にモロッコも帰属を決する住民投票を実施することに応じたが、その住民資格をめぐって決着がつかず、投票も実施されていない。ただし、モロッコと独立勢力は、1991年に停戦に合意し、緩衝地帯を設けて戦闘は収まった。
1990年代から他のアラブ諸国と同じように、モロッコでもイスラーム原理主義運動のテロが起こっている。イラク戦争ではモロッコ政府がアメリカを支持、軍隊を派遣したことに対してイスラーム過激派が反発、2003年には5月にはカサブランカで同時爆破テロが起こり、フランス人・スペイン人などを含む40数名が殺害され、2007年にも同じくカサブランカで爆破テロ事件が起きている。
2020年10月になって、モロッコ軍が西サハラ南部の緩衝地帯で軍事行動を行い、ポリサリオ戦線支持者を排除するという行動を開始し、再び緊張が高まった。国連及び、アルジェリアなど周辺諸国は自制を呼びかけているが停戦が破られる恐れがでている。<朝日新聞 2020/11/17>





